
【活動報告】東京都亜熱帯区 八丈島キャンプ(2025年8月8日~13日実施)
八丈島に到着するまで、幾つかの島を経るため、船内は早朝から何度か明るくなります。夜明けとともに目を覚ました何名かの子どもたちは、朝陽を見たいと言って甲板へ上がりました。窓の外に広がる、まだ仄暗い海の水平線の彼方で、赤々と燃える朝陽に子どもたちは釘付けになっていました。こんなに美しい日の出を見たことは、もしかしたら初めての経験かもしれません。これも、子どもたちの心に残るキャンプの一コマになってくれることを願います。

その後、規定の時間に全員で起床し、簡単な朝食を済ませ、今度は全員でデッキに出ました。すると、目前には深い緑と火山の稜線が印象的な八丈島の姿。長い船旅を経てたどり着いたこの景色は、これからの生活への期待を大きく高めてくれます。


港に到着すると、まずは毎年お世話になっている宿の「柳家荘」へ。今回は、宿の定員目一杯の利用です。
最初に荷物を整理し、部屋の割り当てを確認して、自分の荷物を置く場所、かばんの収納方法を考えました。共同生活のための整理整頓を行うことは、周囲と空間を共有する力を育てます。
また、キャンプ中の基本ルールや安全に関する説明も受けました。海や山で活動する上での危険や注意点を理解することは、自分や仲間を守る第一歩となります。


午後の遊びの前に、昼食は、空港のレストラン「アカコッコ」でいただきます。例年、空港の皆さんが子どもたちのために特別に座席を用意してくださり、この大人数の食事をサポートしてくださいます。島の中では大勢で食事ができる場所が限られるため、このように協力してくださる方々がいらっしゃることに感謝し、島の皆さんの支えのおかげでプログラムが行えていることを実感するときです。子どもたちにも、これが当たり前ではなく、自分たちの体験を支えてくださる方々がいらっしゃることへの感謝を持つ大事さを伝えます。
本日の昼食は、八丈島名物の「明日葉」を用いた、明日葉うどんです。明日葉とは八丈島名産の野菜で、強靱で発育が早く、「今日、葉を摘んでも明日には芽が出る」と形容されるほど生命力が旺盛であることが名前の由来となっています。島で過ごす4日間、元気な毎日過ごせるよう、余すことなくいただきます。




午後からは、いよいよ楽しみにしていた海遊びです。底土海水浴場まで移動し、まずライフジャケットやシュノーケルの装着方法を習い、海に入る前にしっかりと安全確認を行います。


最初は波の感触を確かめるように足を浸けていた子どもたちも、慣れてくると次第に水中へ。透明度の高い海では、小魚の群れや海底の岩がくっきりと見え、「すごい!」「魚がいっぱい!」と歓声が上がります。
何度も飛び込みに挑戦する子、シュノーケルで遠くまで泳ぎに行く子、それぞれの挑戦が見られました。






この時間は、リーダーたちの安全な見守りのもと、それぞれのペースで挑戦を励ますことを特に大切にしています。海への飛び込みは、大人でも少し躊躇する行動です。それにチャレンジするも自由、しないも自由。やってみようとする子を応援する声に後押しされ、最終的に飛んでみる子もいれば、やはりやめておくという選択もありです。それが次に同じ様な場面に遭遇した時への布石になります。



海遊びは、自然との距離感をつかみ、リスクを理解しながら行動する力、判断する力を育てます。波や流れを感じながら、自分自身で選び取って遊ぶ経験は、教室では得られない感覚を研ぎ澄ますことができる、体験的な学びそのものです。
海でたっぷり遊んだ後は、宿で夕食をいただきます。今回は人数が多いのでリーダーも積極的にサポートしながらも、食事の配膳や片付けは、子どもたち自身ができることを協力して行います。


てんげんじこどものいえでのキャンプでは、子ども達が「自分のことは自分でする」習慣を身に着けることを大切にしていますので、 小学生が率先して年下の子の分を取り分けたり、声を掛け合ってテーブルを整えたりする姿は、年齢や立場を超えた助け合いの関係を築く場となります。
就寝準備では、布団敷きやシーツ掛けも自分で行います。はじめは戸惑っていた子も、手順を教わりながら少しずつ慣れ、自ら動けるようになっていきました。


この日の経験は、翌日以降の活動に向けての土台となり、仲間意識と自立心を確実に高める一日となりました。
八丈富士登山に挑戦! ピクニックや温泉入浴など、イベント盛りだくさんの3日目は次のページへ



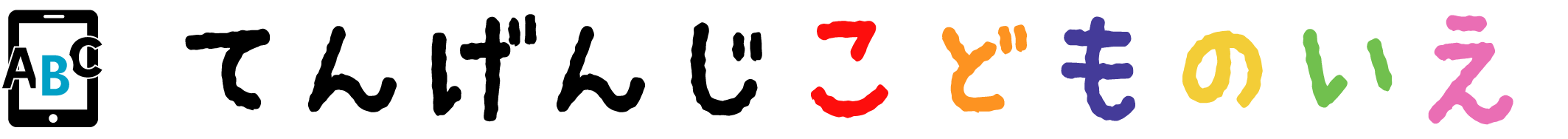




コメント