
【活動報告】西伊豆アドベンチャーキャンプ(2025年7月22日~7月25日実施)
西伊豆の朝は、澄んだ空気と小鳥のさえずりで始まります。子どもたちは、早くもキャンプ生活に慣れ、元気いっぱいな子や、緊張からあまり眠れなかった子まで様々です。
起きたらまずは布団の片づけと朝の健康チェックを行います。大きな布団を子ども一人だけできれいにたたむのは難しいことですが、「そっち持っててくれる?」などと声をかけて、お友達と協力して片づける姿が見られました。

朝の支度が済んだら、校庭でラジオ体操を行い、頭も体もしっかりと目覚めさせます。
前でお手本になってくれる子を募ると、何人もの子が積極的に名乗りを上げてくれました。
体操を終えると、ちょうど朝食の時間になったため給食室へ。バランスの取れた栄養満点の朝ごはんでしっかりとエネルギーを蓄え、これからの活動に備えます。


部屋に戻り着替えを済ませると、午前のメインプログラム、川遊びの準備です。過去のキャンプでは少し下流で遊ぶこともありましたが、今回は宿舎の目の前の一部を区切って遊ぶため、全員で歩いて、川まで降りていきました。
川での活動は、全プログラムの中でも細心の注意を払い、とりわけ安全管理を最優先にして取り組みます。大人も子どもも全員がライフジャケットを着用し、子どもたちは一人一人、リーダーやスタッフが点検していきます。緩んでいるところがないか、きちんとした手順で着られているか。この確認が子どもたちの命を守ることにつながります。



全員の準備が整うと、リーダーが先行し、上流と下流、さらには深くなっているところの手前に立ちます。子どもたちにも「リーダーの立っている範囲を超えない」という約束を確認し、安全第一な万全の体制を築きました。
川の中に入ると冷たくて澄んだ水に思わず「冷たい!」と声が上がります。


複数の大人が見守る中、少し深いところでボートから川に飛び込んだり、水鉄砲で友だちと水をかけ合ったり、岩の上を慎重に歩いたりと、それぞれが思い思いに自然とふれ合います。
ある子が「カニがいたよ!」と叫ぶと、周りの子も興味津々で見に行きます。すると別の子が、「石を積んでカニのお家を作ろうよ」と言い、自由な発想で、様々な遊びが展開されていました。






自然の川は、やや深くなっているところや、岩が多いところなど、人工的な遊びの環境とは異なって、子どもたちが自分で気をつけなければならないことも多くあります。そうした中でも、ライフジャケットを着るといった用具の安全と、リーダーたちの注意をよく聞いて臨むことで、子どもたちは臆することなく、果敢に自然の中の遊びに挑んでいました。夏の強い日差しの中では、川の水の冷たさが心地よく、子どもたちは時間いっぱい元気に川遊びを楽しみました。
遊び終わった後は、持ってきた水筒と塩分タブレットで、しっかりと水分と塩分を補給しました。遊びに夢中になるだけでなく、体調管理にも万全を期したところで、宿舎へと戻ります。冷たい川の水を温かいシャワーで流し、さらにもう一度温泉プールに入って、川で冷えた体を少し温めてホッと一息つきます。



プールでも少しの時間、遊んでから、体をしっかりと拭いて部屋に戻ると、着替えて昼食の時間です。
濡れた水着を干したら、グループ全員でお弁当を受け取って部屋へ。グループごとでも「いただきます」「ごちそうさまでした」のあいさつはしっかりと行います。

この日のメニューは鶏のから揚げ弁当。涼しい部屋で火照った体を冷ましつつ、子どもたちはお腹いっぱいに食べ、午後の活動に向けて元気を蓄えました。
食後、お弁当の容器は分別して重ね、机や周りに落ちた食べこぼしの片付けはみんなで協力して行います。自分たちの借りている部屋ということだけでなく、他の人も使う部屋ということを意識し、綺麗に掃除します。
昼食後はしばしの自由時間を設け、子どもたちは疲れを癒したり、友だちと談笑したりしてのんびりと過ごしました。
そうして少し時間がたったころ、おやつのかき氷が提供されました。シロップはいちご、メロン、ブルーハワイの3種類から好きなものを選ぶことができます。



待ち時間は日記を書くなどして有効活用しつつ、きちんと列に並んで、自分の番を待ちます。中には、「シロップ全部かけてもらっちゃった」と3色に染まった氷を見せてくれる子や、「もっと食べたいな」と空の器を見つめる子もいました。暑い日にぴったりのひんやりスイーツに、子どもたちは大喜びでした。
冷たいかき氷でリフレッシュした後は、午後のメインイベント、待望の野外炊事です。キャンプの醍醐味とも言えるこのプログラムでは、子どもたちがチームに分かれて火おこしや調理に挑戦しました。
スタッフの指導のもと、飯ごうでのお米の量り方や火の管理方法を学び、安全に注意しながら火を起こしていきます。安全管理上の事項として、「燃えている火の後ろは通らない」「軍手を必ず着用する」「火の前では座り込まない」といった約束を確認します。薪の積み上げ方やマッチの擦り方など、初めての経験に戸惑う子もいましたが、リーダーやスタッフがサポートしながら、みんなで協力して徐々に火が安定していく様子に大きな達成感を感じていました。
今回のメニューはカレーライス。まずはグループの中で、火おこしをしてお米を炊く人、野菜や肉を切る人、と役割を分担します。
火おこしチームは、かまどに組んだ木の中央に置いた新聞にマッチで火をつけ、うちわで一所懸命に風を送りながら火をおこします。ある程度火がおこったら、飯ごうをその上に置き、注意深く炊きあがりまでの火かげんを調整し続けました。やがて飯ごうの蓋の隙間から水が溢れ出てくると「水が出てきた!」と歓声を上げ、お米がどのようにして炊けるのか、初めて知ったという子もいたようです。



火おこしやご飯の用意と並行して、具材の下ごしらえも行います。リーダーから、包丁を使うときは猫の手で押さえるなどのアドバイスを受けつつ、「玉ねぎが目にしみるよ。」と苦戦する声も聞こえてくる中、やっとのことで全部の食材を切り終えました。




ご飯が炊きあがると、いよいよカレー鍋を火にかけます。肉や野菜が焦げないようにかき混ぜるのですが、大きい鍋いっぱいに入った野菜は、子どもたちには一苦労です。「次は僕が代わるね」と声を掛け合いながら、協力して鍋を混ぜ続ける頼もしい姿も見られました。ある程度炒めたところで水を入れ、じっくりと煮込みながら、美味しいカレーができるよう祈りながら、調理の後片付けを行いました。


しばらくしてルーを割り入れ、いよいよカレーが完成です。熱々のカレーをみんなで味わうと、そのおいしさに思わず笑顔があふれました。「おかわり!」の声があちこちから聞こえる中、「僕たちのグループが一番おいしいんじゃない?」という感想が思わず飛び出す子も。自分たちで作った料理の味は格別です。



こうしてカレーを味わった後は、協力して最後の片付けタイムです。まだ洗い残していた調理道具や食器、飯ごうや大鍋を全員で手分けして洗います。中でも、ある小学生の男の子が「机の上をきれいにしたいんですけど、拭けるものはありますか?」と聞いてくれたことが非常に印象的でした。周囲の状況を見ながら自分にできることを探し、気づいて実行することができるという姿や、昼食の際にリーダーから言われた食後の机をきれいにするということを忘れずできるようになっているという姿に成長を感じる一幕でした。




その後、洗い場の広さの関係で、先にお風呂に行くグループと残って片付けをしてもらうグループの2つに全体を分けるなどしながら場所と時間を上手に使い、最後まで責任を持って後片付けを行いました。
宿舎に戻ると、1日目で要領がわかった子どもたちはてきぱきと寝具の準備も済ませ、就寝準備を進めることができました。たくさんの体験を重ねて少し疲れたのか、子どもたちは就寝時刻を過ぎるとすぐに寝息を立て始め、2日目の夜も、静かに更けていきました。




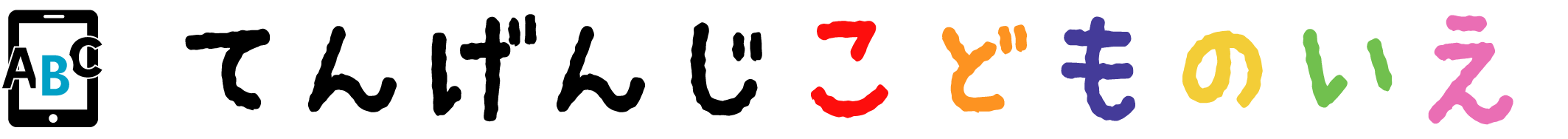




コメント