
【活動報告】西伊豆アドベンチャーキャンプ(2025年7月22日~7月25日実施)
3日目のメインプログラムは自分のやりたいことを自由に選んで挑戦できる「Challenge by Choice Time (チャレンジ バイ チョイス タイム)」です。今年から施設を貸切にしたことで、プログラムの自由度がさらにパワーアップし、子どもたちの主体的な活動を促す時間・空間のゆとりを確保しました。
この時間では、子どもたちが自分自身の興味や好奇心に従い、「やりたいこと」に心ゆくまで挑戦することができます。
前日の聞き取りやスタッフが毎日実施している振り返りミーティングで、「もう一度プールに入りたい!」という子どもたちの声が多数あがったため、午前の活動は全体でのプール遊びとなりました。
温泉プールでは、昨日よりもさらにリラックスした雰囲気の中、それぞれが自由に水と戯れました。浮き輪に乗って流れに身をまかせる子、水泳の練習をする子、水中での追いかけっこを始める子など、遊びのスタイルは多種多様。大人の提示によるプログラムだけではなく、自発的に生まれる遊びがあちらこちらで繰り広げられ、自然な笑顔と歓声がプールに響いていました。



スタッフたちは常に安全に目を配りながらも、遊びのパートナーとして一緒に水中に入り、子どもたちに寄り添いました。中には、前日はリーダーに手を引かれながら泳いでいた子が、「みて、一人でも大丈夫になったよ!」と言いながら泳いでみせる姿もあり、子どもたち一人一人の挑戦や楽しみ方に合わせて過ごせるこの時間は、まさに「チャレンジ バイ チョイス」と言えるひとときとなりました。
そんな中、自然と「チームでなにかやってみたい」という声があがり、即席の水上運動会がスタート。やってみたいと集まってきた子どもたちの表情はとても生き生きしていました。
大玉送りでは、チームで協力し、巨大なビーチボールをコースの反対側まで運びます。子どもチームの挑戦では、「全員で一緒にいるんじゃなくて、コースに散らばったほうがいいんじゃない?」などとアドバイスをし合いながら、25メートルのプールを30秒ほどかけて渡しきりました。途中ボールがコースアウトしてしまう場面もありましたが、「私が取ってくる!」と言ってボールを戻す子と、水中で受け取る子で上手に連携しながら力を合わせることができていました。大人チームの挑戦時には「リーダーも頑張れー!」と声援を送ってくれる子もいて、笑顔と歓声が絶えない時間となりました。


続く水泳対決は、小学3・4年生の部、小学5・6年生の部、大人の部に分かれて行われ、泳ぐのが得意な子もそうでない子も、みんな一所懸命に泳ぎ切りました。
普段は頼れるお兄さん・お姉さんのリーダーたちが本気で泳ぐ姿を見て、「今度は大人対子どもでリレー勝負してみたい!」と競争心を燃やす姿もあれば、「次は一番になれるようにしたい」と決意を新たにする子もいて、次なる目標に向かっていく姿が印象的でした。


この運動会は、あらかじめ決められたプログラムではなく、「やってみたい!」という声を拾って即興で構成された体験であったことが、子どもたちの主体性や満足感をより高める結果につながったのではないかと言えます。参加しなかった子たちも、自分のペースで水と親しみながら、時には友だちを応援したり、声をかけたりと、それぞれのスタイルで楽しんでいました。
昼食は昨日と同じくお弁当です。リーダーに言われなくても、自主的に食べ終わった容器を重ねたり、机を拭いたりする様子が見られ、わずか一日での子どもたちの変化に驚かされました。
午後の活動も引き続き「チャレンジ バイ チョイス」の時間。午前とは異なり、ここでは個人や小グループで好きなことを選び、自由に過ごす形式がとられました。それぞれの選択は本当に多様で、まさに「自分のやりたいことに向き合う時間」となりました。
ここで出たのが「野球がしたい!」「虫取りがしたい!」という意見。その声にリーダーが応え、外遊びグループが生まれます。日差しが非常に強かったため、日焼け止めをしっかりと行い帽子と水筒を手に、グラウンドや茂みの中へ元気よく飛び出しました
何人かの男の子たちは野球などの球技に熱中していました。使っていたのはなんと、タオルのバットに丸めた軍手のボール。道具がなくても創意工夫で何でも遊びに変えてしまうのは、子どもたちの独創性や柔軟な発想の表れと言えるでしょう。
リーダーからも適宜休憩をとるように声を掛けながら、「次は僕が投げるね」などと互いに声を掛け合い、グラウンドにいつまでも歓声を響かせていました。


虫取りグループは、リーダーと一緒に夏の昆虫を探して校庭の周囲を散策。バッタやカマキリ、チョウに加え、蝉の抜け殻などを発見し、その一つ一つに子どもたちは目を輝かせていました。「ほら、あそこにいたよ」と声を掛け合いながら虫取りに熱中し、お友達が捕まえたときには、まるで自分のことのように喜ぶ場面もありました。
ある年長の男の子は、小学生のお兄さんから借りた網でバッタを捕まえ、「自分一人で捕まえられたの初めて!」と誇らしげに虫かごを見せてくれました。



別の女の子たちからは、「ハンモックづくりがしたい」という意見があり、スタッフのサポートのもと、どこにロープを結ぶのかなどを自分たちで相談して決めました。そうして完成したのはなんと、子どもたちの背丈ほどもある高さのハンモック。途中からほかのグループのお友達も加わり、眼下に広がる山々を見下ろしながら、「いい眺めだね」と言葉を交わしていました。


また別の子どもたちは、屋外での活動ではなく、室内でゆったり過ごすことを選びました。夜のキャンプファイヤーに向けた出し物の相談をするグループもあれば、絵を描いたり日記をつけたり、リーダーやお友達とカードゲームを楽しんだりする姿も見られました。

3時になり、おやつタイムの連絡が入りました。本当は昨日だけのはずだったかき氷も、厳しい暑さを考慮して、急遽追加で提供され、各々が持ってきたお菓子と冷たいかき氷で一息つきました。
前日とは違う味のシロップを選ぶ子もいれば、「やっぱりこれ!」と同じ味を楽しむ子も。友だちと和やかに語り合いながら、夢中でスプーンを動かす姿に、疲れも吹き飛ぶような笑顔が広がりました。



午後は、それぞれの選択によって時間の流れが違って見える、不思議な豊かさを持った時間となりました。「チャレンジ バイ チョイス」の本質は、なにを選んだかではなく、「自分で選んだ」という事実そのものが、子どもたちの自信や自己肯定感につながっていくところにあります。
「自分で決めて、挑戦してみた」その達成感が、子どもたちの表情や姿勢にしっかりと刻まれた1日となりました。
夕食後、夕日が山の端に沈んだ後、いよいよキャンプファイヤーの時間がやってきました。合図とともに、今回の参加者で最年長の女の子たちが火のついたトーチを持って入場し、組み木に火を灯すと、乾いた薪がパチパチと音を立てて燃え上がり、夜の闇を明るく照らします。火を囲む輪に子どもたちが集まり、「燃えろよ燃えろ」を歌うと、火を囲む雰囲気がぐっと高まります。


まずはウォーミングアップに、全員で「猛獣狩り」のゲームを楽しみました。本来は、指定された動物の字数と同じ人数になるように手をつなぐゲームですが、今回はキャンプバージョンということで、「にしいず」「やまびこ荘」「カレーライス」のように、キャンプにちなんだ言葉が選ばれました。テンポよく続くリズムに、子どもたちは夢中で参加し、お友達と一緒に手をつないで、体も心もほぐれていきます。
つづいて、スタッフから「洗濯一週間の歌」を教わりました。
歌に合わせ、曜日ごとにいろいろなポーズを取ると、子どもたちからは思わず笑みがこぼれます。「何このポーズ!」などの言葉を口にしながら、大盛り上がりの時間になりました。
続いて、各グループによるスタンツ(出し物)の時間です。それぞれが事前に話し合って決めたものを披露し合います。「じゃんけん列車」で長い列を作って盛り上がったり、「怪獣のバラード」をみんなで一緒に歌いながら簡単な振り付けをつけて踊ったりと、笑いと拍手が絶えない時間となりました。中にはリーダーを巻き込んだユニークなパフォーマンスもあり、音楽と遊びにあふれた時間が続きました。



やがて火が少しずつ小さくなってくると、静かな雰囲気の中で「漕げよマイケル」を歌いました。歌声が夜空に響く中、ふと見上げれば満天の星空が目に映ります。都会ではなかなか見ることのできない夜空に、「あれ天の川じゃない?」「え、どこどこ?」という声も聞こえました。
そうして徐々に、火が小さくなると、待ちに待ったマシュマロが登場します。スタッフが焚き火の周りに新しく薪を置き、「この薪を越えて火に近づかないように」と注意事項を伝えます。リーダーたちも注意深く見守る中、子どもたちは、一列に並んで、串に刺したマシュマロを受け取ると、焚き火のまわりに集まって炙り始めました。
「もう焼けたかな?」「もうちょっと焦がしたほうがおいしいと思う」と好みの焼き加減を求めてじっと待ちます。椅子に戻り、こんがり焼けたマシュマロをクラッカーに挟んでほおばれば、香ばしくとろける甘さに、子どもたちからは自然と笑顔がこぼれました。

キャンプファイヤーが終わると、辺りはすっかり夜の静けさに包まれていました。部屋に戻り、歯磨きを済ませて布団に入ると、遊び疲れた子どもたちは、すぐに静かな寝息を立てていました。



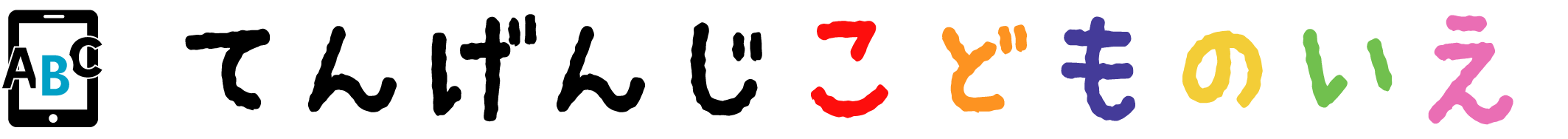




コメント